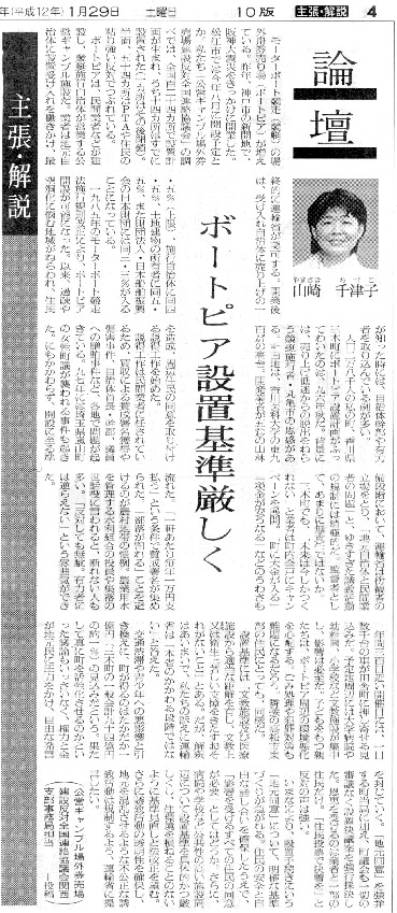�{�[�g�s�A�ݒu��������@�@�@�@�_�d�@�����V���i���{�Ёj�@2000.1.29
�R���Îq
���[�^�[�{�[�g����(����)�̏�O�M�������(�{�[�g�s�A)�������Ă���B��N�A�_�ˎs�̐V�J�n�ŁA��_��k�Ђ����������ɊJ�Ƃ����B���]�s�ł͍��N�����ɊJ�ݗ\��Ƃ��B�������u���c�M�����u����O�����ꌚ�ݔ��ΑS���A�����c��v�̒��ׂł́A�S���S��\�l�J���Őݒu�v�悪���܂�A�����\�l�J���͂��łɐݒu���ꂽ�i��J���͂��̌���j�B���ʁA�\�l�J����PTA��Z���̔S�苭�����łԂ�Ă���B
�{�[�g�s�A�́A���ԋƎ҂Ȃǂ����݂��A�����{�s�����̂��c�Ƃ�����c�M�����u���{�݂��B�Ǝ҂͒n�������̂ɐݒu����������A�ŏI�I�ɉ^�A�Ȃ��F����B�J�ƌ�́A���ꔒ���̂ɔ���グ�̈�E��% �i����j�A�{�s�����̂ɓ��l�E��%�A�y�n�����̏��L�҂ɓ��܁E��%�A�܂����c�@�l�E���{�D���U����̓��{���c�ɂ͓��O�E�O%�����邱�ƂɂȂ��Ă���B
��㔪�ܔN�̃��[�^�[�{�[�g�����@�{�s�K�������ɂ��A�{�[�g�s�A�J�݂��\�ɂȂ����B�ȗ��A�ߑa����ɔY�ޒn�悪�˂���A�Z�����m�������ɂ́A�����̊�����L�͎҂���荞��ł���Ⴊ�����B
�l���������l�̎��̒��A���쌧�O�ؒ��Ƀ{�[�g�s�A�ݒu�v�悪�ӂ��Ă킢���̂́A��Z�N�H���B�w�i�ɂ́A����グ�������̒E�o���˂炤�����{�s�ҁE�ۋT�s�̎v�f������B�v��n�́A�����ȑ�w�̓���S�b�̍���B�J���Ǝ҂��S�f�̎R�т��A���ӏZ���̓��ӂ����t��������H����n�߂��B
�����H��͖��ԋƎ҂ɔC����Ă��邽�߁A�����ɂ��^�������l���⏝�Q�����A�����̎E�����A�c���ւ̑��d�����ȂǁA�e�n�Ŗ�肪�N���Ă���B�㎵�N�ɂ͍�ʌ����R���̏������c���P���鎖�����N�����B�ɂ�������炸�A�J�݂Ɏ��鏀���i�K�ɂ����āA�^�A�Ȃ͖T�ώ҂̗�����Ƃ�A�u�n�������̂Ɩ��ԋƎ҂̖��v�ƁA�䂫�������U�v�����̋K���ɂ͏��ɓI���B�ē҂Ƃ��āA���܂�ɖ��ӔC�ł͂Ȃ����B
�O�ؒ��ł��A�u�����͍���������Ȃ��v�ƋƎ҂͒����S�˂ɃL�����y�[����W�J�B�u���ɑ��������v�u�ŋ��������Ȃ�v�Ȃǂ̂��킳�����ꂽ�B�u�ꌬ�����薈�N�ꖜ�~�x�����v�Ƃ��������Ŏ^���������W�߂�ꂽ�B�u�����������v���Ƃ������̂��_���n�т̊���B�_�Ɨp�����Ǘ����鐅���g���̖�����W���̐��b���Ɍ�����ƁA�f��Ȃ��l�������B�u�����Ă����ʁB�L�͎҂ɂ͋t�炦�Ȃ��v�Ƃ������͋C���ł����B
�N�ԎO�S���߂��J�Ó��ɂ́A�ꌎ�����̎Ԃ��c�ɒ��ɉ����錩���݂��B�\��n���ӂɂ͑�w�a�@��c�t���A���w�Z�ȂǕ����{�݂��W�����A�e���͕K�����B�q�ǂ������e�����́A�{�[�g�s�A���ӂ̊�������S�z����B���ݏ�����ƍߑ�����ɂȂ邾�낤�B�אڂ̍����s�����̏Z���ɂƂ��Ă��A���l���B
�ݒu��ɂ́u�����{�y�ш�Î{�݂���K���ȋ�����L���A�����㖔�͉q�N�㒘�����x��������������ꂪ�Ȃ����Ɓv�Ƃ���B�����A���߂͂����܂��ŁA�������̑i���ɉ^�A�Ȃ́u�{�Ȃ̂������i�K�ł͂Ȃ��v�Ɠ������B
��ʏa����N�ւ̈��e���ƈ��������ɁA��������̂͂��������ꉭ�~�i�O�ؒ��̈�ʉ�v��\�l���~�̖��%�j�̌����݂��Ƃ����B�ʂ����Đ^�ɒ���������������̂��Ƃ������c�_�����������Ȃ��A���͂Ƌ����n�����Ɉ��͂������A���R�Ȕ������Ă����B�u�n�����Ӂv�����ق��钬���ǂɉ����A���c�����̐R�c�Ȃ��ݒu���c�Ă����s�̌������B���b����̂͋Ǝ҂ƈꕔ�̏Z�������B�u�Z�����[�Ō������v�Ɣ��̐��͋����B
���܂Ȃɂ��A�ݒu�葱���ɂ����u�n�����Ӂv�ɂ��āA���m�Ȋ���肪�}�����B�Z���̈��S�Ǝ��R�Șb���������m�ۂ��������ŁA�u�e�����邷�ׂĂ̏Z���̓��ӂ��K�v�v�Ƃ��Ă͂ǂ����B����ɁA�a�@��w�Z�Ȃnj������̍����{�ݎ��ӂɂ��Đݒu�����̓I�����������A�Z���˂邱�Ƃ̂Ȃ��悤�Ɋ�������Ɩ@������]�ށB����ɗU�v�����̓��������m�ۂ��A�n��������������悤�ȕs���~�ȗU�v�����͋K������悤�A�^�A�Ȃɒ������B
���c�M�����u����O�����ꌚ�ݔ��ΑS���A�����c����x�������ǒS��