|
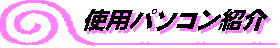
・メインコンピューター・・・自作IBM PC/AT互換機(DOS/V)
マザーボード:SERVEX SV-119
RIOWORKS PSVA(AGP4X対応、音源なしバージョン)
ABIT ST6(socket370 Intel 815EP B-Stepチップセット)
ASUS P4PE+A/L(socket478 Intel 845PEチップセット)
CPU:AMD K-6 233MHz(66MHzx3.5倍速動作)
Cyrix MII 333GP(75MHzx3.5倍速動作)
Intel Celeron 400MHz PPGA(66MHzx6倍動作)
Intel Pentium!!! 800EB FC-PGA(133MHzx6倍動作)
Intel Pentium4 1.60AGHz mPGA478(Northwoodコア)(FSB400MHz)
メモリ:パナソニック SDRAM 64MB 詳細不明
HYUNDAI HY57V658020BTC-75
KINGMAX MPGA83S-883
をそれぞれ使用したSDRAM 128MB
PC133
CL3
何かのSDRAM 256MB PC133 CL2 2枚
PC2700 DDR 256MB 333MHz
PC2700 DDR 512MB 333MHz
VGAカード:ASUS AGP-V3000(RIVA128)4MB VRAM
ASUS AGP-V3800Pure(RIVA
TNT2)
16MB VRAM
ATI RADEON DDR VIVO(64MB)
SCSIカード:Logitec LHA-521UA
今のところ問題なく動作しているようです。プラグアンドプレイというものはどうも眉唾物で、共有が起こるとやはり不安定になる率が高くなると感じます。逆の事を言うようですが、うまい具合に共有できれば2つ以上の共有が起こっても安定動作するようです。BIOSにもよるのでしょうか?最近のマザーボードではそれほど問題になることはなくなりました。
サウンドカード:CREATIVE SoundBlaster Live!(初代)
発売当初に思い切って買っちゃいました。以前使っていたISAの安物に比べて音質も速さも申し分ありません。某KeyのゲームではBGMボリュームフェードアウトが効かないのですが、今は改善されているようです。(というか、やっぱり環境によりけり・・・)次はこれを越えたと言われるオンキョーのカード(SE-120PCI)をねらってみたいなぁ。
そして2001年の秋、ついに次世代のサウンドブラスターが登場しました。augidy(オージディー)でしたっけ。なんでもチップの性能はLive!の4倍だそうで。スペック的には96KHzサンプリングが出来たり興味をそそる製品ではあります。ソフトウェアでCUBASIS
VSTがついてくるというのもおいしい。英語版だそうですが。
ハードディスク:Western Digital WD450AAA(45GB)UltraATA66
QUANTUM Fireball CR(8.4GB)UltraATA66
IBM IC35L080AVVA07(80GB)UltraATA100
フロッピーディスク:TEAC FD-235HG
3モードにも対応してますがマザーボードが対応してないのでソリトンウェーブ社のFDC-3Dを付けて対応させています。自動切り替えなのでなかなか使いやすいです。
CD-ROMドライブ:Aopen CD−932E 32倍速
Logitec LCD−Z40AK 全周40倍速
BTC BCD40XH 40倍速
HITACHI GD−7500(DVD−ROM)
pioneer DVD−104(DVD−ROM)
最近はDVD−ROMドライブでも1万円以下で買えるようになりましたね。で、比較的新しいこのドライブ、父のpioneerのドライブが風切り音がかなりうるさかったので、静かだという噂のあったHITACHIのドライブにしてみました。動作音は噂どおり静かです。読みとり自体というより、回転停止状態から再びデータを読み込むときにかかる時間が短いです。難点といえば難点かもしれませんが、トレイの出し入れ音は大きいです。「ギヤ〜−」っと出てきます。その点はpioneerのスロットインが便利だなぁと感じることもありますね。
・・・その後読み込みがへたれてきたので(-_-;ゥ、結局今はpioneerのを使っています。
CD-Rドライブ:TEAC CD−R55S
レーザーが甘くなったとか言う理由で、これも弟のお下がり。ですが、使えてますよ、これ! CD-RWは使えませんし速度も遅いですが十分十分! まあ、問題はこれで焼いたCD-Rがいつまで保つかですが、そんなのわかんないも〜ん^_^;
CD-RWドライブ:MITSUMI CR-48X8TE
よく分からないことがあるのですが、CDのデュプリケートソフトなどでベタ読みさせたときに、このドライブではエラーを返すが上のTEACのドライブではエラーを返さないということがあります。これはTEACの方が性能がいいということなのでしょうか? それともいい加減ということなのでしょうか。いずれにせよエラーは出ない方がいいので読み込みにはTEACを使うことが多くなります。それ以外の用途ではさすがに新しいドライブですから不都合なことはないです。
・その他周辺機器
モニターディスプレイ:TOPFLY 15インチCRT
TAXAN ERGOVISION151
ICM LS-2617FN
SONY CDP-17sf7(譲ってくれた友人にthanx!)
モデム:NISSEI FM3314 33.6kbps
I・O DATA DFML-560 V.90/K56flex規格対応 56kbps
LAN:corega FastEther II PCI-TX
メルコ BUFFALO LGY-PCI-TXC
オンボード(BroadCom BCM4401)
プリンタ:EPSON HG-2550
プリンタ:EPSON PM-760C
ついに買ってしまいましたよ、今時のフォトインクジェットを!それも数量限定の特価品を朝からお店の前に並んで・・・まあ並んでと言っても30人レベルの話ですけどね。USBにて接続。マザーボードのリソースが足りるのかとかちょっと心配しましたが、全く問題なし。実はIRQの共有は2つまでかと思っていたら、3つでも出来てしまうようです。
さて、実際の使用感は普通紙でもそれなりに綺麗ですね。高画質はさすがに時間がかかりますし、テスト印刷など繰り返していたらあっという間にインクが無くなります。(それで買ってきた値段半値ほどの非純正インクが、なんか臭いのには笑った^^;) 画面とのカラーマッチングをとるのがかなり難しい、と言うか根気が要りそうです。プリンタドライバーや印刷時に出てくるプリンタウィンドウも順当に進化しているようです。インク残量がリアルタイムで確認できたり、プリンタに関する今日の一言みたいな物が表示されます。下から二つ目のグレードだし安く買えたし、十分満足です。
プリンタ:Canon BJ-330J 上のHG-2550を手放すことを決定づけた一品。某ローカルパソコンショップでは「ご自由にお持ち帰り下さい」と書いて、中古でも値の付かなさそうな古いパソコンパーツを店先に並べていたりしますが、そこにおいてあったコレ。モノクロだけどバブルジェット。サイズ的にもB4横置き可能でHG-2550と同じ。何が私の心を捕らえたかというと、こいつには穴あきのフェーダー紙を利用できるトラクターユニットが標準装備なのであります! なぜだか家にはフェーダー紙がいっぱいあるのです。時にながーい文章を印刷する必要があるときはこっちの方が好都合な感じです。ホビー向けと言うよりビジネス向けなためか、実際動作もきびきびしていて気持ちがいい動きをしますし(ところが実際の印刷は遅いのです)、印刷品質も綺麗です。
こいつの難点、というか特殊な点はコントロールカードというICカードが無いとさっぱり動かないということ。幸いにしてそれも一緒に出されていたので抜かりなくゲットしてて良かった^^;
で、本当の難点はディップスイッチによる機能設定がめっちゃくちゃややこしい点。持って帰ったそのままでも使えたのでしょうが、善意でその解説をしてくれているHPに行き当たらなければお手上げでした。次はカットシートフィーダーがよほど綺麗な紙を使わないと、2〜3枚どころか5〜6枚でもいっぺんに引き込んでしまう点。まあコレは本当に故障しているのかもしれませんが。
そして極めつけがWindowsではマイクロソフトが提供しているユニバーサル(汎用)ドライバを使うわけですが、何の兼ね合いが悪いのか印刷範囲が普通のA3プリンタほどに設定されていて、B4横置きの半分ほどしか印刷しない点。意味無いじゃん! しかしコレにも解決策はありました。Canonも言っているように例のコントロールカード、実はEPSONプリンタのエミュレーションカードだったりします。だからWindowsでEPSONのそれらしいプリンタ用のドライバをあてがってとりあえず一件落着(笑) なお、この現象はWindows2000やXPでは直っているみたいです。
・DTM(パソコン音楽)環境
外付音源 :YAMAHA MU2000
Roland SC-8850
Roland UA-30(USB AUDIO INTERFACE)
KAWAI GMega(予備)
Roland CM-64(もはや置物^^;)
入力用鍵盤:Roland PC-180
YAMAHA CBX−K1、CBX−K2
上のPC-180には唯一と言っていい弱点がありました。それはノートナンバーの0〜127全てをカバーしていないというものです。見た目鍵盤は49鍵4オクターブしかないので、それ以下とそれ以上の音は仮想的に鍵盤をずらす事で対応するのですが、その、ずらせる範囲が最近の物に比べて少ないと言う事です。尤もグランドピアノが88鍵であり、127鍵のキーボードという物が存在しないように、そんなに高い音や低い音はあまり意味がないのですが、MU128のドラムパートにはPC-180ではカバーできなかった範囲がありました。それだってかなり特殊な音色であまり使う頻度は少ないとは思いますし、キーボードからでなくてもシーケンサーのデータ上で鳴らす事は可能なので、その範囲の入力を容易にするなど考える人は少ないかもしれませんが。で、標準鍵のPC-180は場所をとっていたなあと思い、今度はミニ鍵盤でMU128に合わせてYAMAHAで、ということでCBX−K1を購入する運びとなりました。実際、小さくてコンパクトなのはGood! んがー(本当に、んがー!)、触れて初めて分かる事、何なのでしょう、この粘土ゴーレムを押すようなキータッチは! ちょっとバネが強すぎるのでは。オクターブ以上の音が片手で押さえやすいなどの利点はあるものの、今まで標準鍵に慣れていた私は即、肩こり全開となりました;;これは辛いなぁということで、これまた速攻で標準鍵タイプのCBX−K2を購入しましたさ。あぁ、やっぱり標準鍵だわ。キータッチはPC−180よりちょっと軽いくらい。場所は取るけれども長く使って疲れない方がよほど重要。でも相変わらずリアルタイム入力をするわけではないのになぁ^^;
ミキサー:KAWAI Mixas
リサイクルショップ「ハード・オフ」からの救出物。本体\400と電源アダプター\400で、なんと800円!
アンプ :Technics SU-X70
PIONEER A-X7
PIONEER A-D3
ピュアオーディオ用アンプなのでパソコン用にはちょっともったいない!?・・・音はともかく、これにしてから左の音がえらく大きくなったように感じるのは気のせい??
元々私の耳は左を大きく感じるんですけど結構気になってしまうものです。
スピーカー:ナショナル SB-46
PIONEER S-X33
往年の銀色コンポの一部で、前の物より大分マシです。
ソフトウェア:COMEON MUSIC レコンポーザ95
Release3
グラフィカルなインターフェースでアナログ感覚の編集をするという最近メジャーなことは出来ませんが、なによりも動作の軽さと数値入力が私に合うのでDOS時代から愛用しています。私の偏見かもしれませんが、数値を直接見ながら編集しないと、編集を重ねると重ねるだけ無駄なデータが増えてしまう気がして、それが演奏の乱れを起こしてしまう気がして気持ち悪いんですよね^^;
Steinberg CUBASIS VST
これは、MIDIでの一括演奏データではなく、waveファイルやCD-DAへ落とすときに、最終のミキシングツールとして使用しています。本CUBASIS(キューベーシスとか読むらしい)はCUBASE(キューベース)の弟分なので、同時に利用できるトラック数などに制限がありますが、それでもステレオで4チャンネルありますから。なんと言ってもこいつのすごいところは、画面に音響卓そのもののグラフィックが表示されているところで、そのボリュームやEQやエフェクトのつまみを動かすとリアルタイムで音が変化し、もちろんそれをWAVEファイルに出力する事が出来る点です。最近のMIDIシーケンスソフトはCAKEWALKやSingerSongWriterにも見られるようにオーディオ編集が充実してきていますが、CUBASE、CUBASISはオーディオ編集部分については先駆けといえる物かもしれません。
YAMAHA XGWorks4.0
オートアレンジャーが結構使えます。ので、最近はこれを最初に使って曲作りしています。
TMIDI Player
Fummyさん製作のフリーのMIDIプレーヤー。多くの種類のMIDIデータに対応している上、RolandとYAMAHAの楽器の差異もある程度吸収してくれるので便利です。バージョンアップされるのも早いです。
|